お読みいただきありがとうございます。
sstです。
勉強法第二弾です。今回は、高速で読みながら内容を忘れない方法について勉強しました。
今までに何冊か速読の本を読んでみましたが、一つとして身についた試しがありません。できるようになるイメージが全くわかないんですね。速読ができるのは、一部の限られた才能を持った人間だけなのかもしれません。
それでも、早く読めるようになりたい、という願望はずっとありました。そんな思いの中で手に取った本がこちらです。
タイトル:死ぬほど読めて忘れない高速読書
著者:上岡 正明
ちなみに、著者が言っているのは、高速読書であって、速読ではないんですね。目的は、早く読むことではなく、本を早く読み、かつ読んだ内容を身に付けること、です。
※脱線しますが、本の中で、年収1000万円以上の人は、この本が書かれた2019年当時で3%程度しかいないと言っており、そのレベルのビジネスパーソンは1か月に7冊程度の本を読むそうです。高速読書で10冊/月くらい読んで内容を身に付けることができれば、たちまちトップレベルの仲間入りということになりそうですね。
そのために以下を推奨しています。
- 本を読む目的を明確にする
- 繰り返し読む
- アウトプットする
本を読む目的を明確にする
なぜ目的を明確にすべきなのか。それは、目的を明確にすることで、自分が探している情報を見つけやすくなるからです。例えば、辞書で何か言葉を調べるときは、1ページ目から全部読んだりしないはずで、必要なページを直接見に行くと思います。
目的をもって本を読む、というのは、辞書と同じことをすればいいんですね。ただ、辞書と違うのは、求めている情報が目次などに必ずしも書かれているわけではないという点です。
そこで、まずは全体に素早く目を通し、必要な情報が書かれている箇所に目印を付けるなどしてピックアップします。この必要な情報への感度を高めるために、目的を明確にするということになります。目的外のところはドンドン飛ばしていきましょう。
繰り返し読む
本を読む目的を明確にして、どこに目当ての情報があるかがわかったら、今度はそこをしっかり読み込みます。1回ですべてを頭に入れる必要は全くなく、著者は本を複数回読むことを前提として気楽に読むことを推奨しています。
2回目に読むときは目印を付けたページだけを読み、筆者が言いたいことは何なのかを整理しながら読む「つまり読み」をします。このあたりの、内容を整理しながら読む、というのは、以下の記事に通ずるものがあると思います。
本を自分で要約するための方法を学んでみた
※こちらの記事では、思考整理によって内容を端的に言い表す方法について書きました。
3回目はアウトプットノートに具体的な行動プランを残すことをイメージしながら読みます。このとき、本に書き込みもガンガンしていきます。私は図書館で本を借りたりするので書き込みはしないタイプですが、書き込んだ方が記憶への定着がよいそうですね。書き込むときに持った印象も効果があるそうなので、血肉とするために感情を込めて書き込むのがよいと思います笑
アウトプットする
アウトプットは、私が思うに著者が最も重視している部分です。読んだ本を自分のものとするというのは、結局のところ、本から学びを得て、自分の人生に活用することに他なりません。読んで頭に入れただけでは意味がないんですね。
そこで、目的を達成するための学び(=エッセンス)を行動に移すために、エッセンスとともに具体的な行動プランを書き残すことを推奨しています。ポイントを押さえた端的なメモとすることで、記憶しやすくするのです。
字数は20字程度。このあたりの文字数も先ほどの記事と同じですね。頭に入る文章量というのは大体決まっているのかもしれません。
内容を簡単にまとめます。
繰り返し学習と行動を伴うアウトプットが重要
- 何を学んだか
- 本を読む目的を明確にする
- 目的に合った部分を繰り返し読む
- 行動を伴うアウトプットをする
- なぜ重要か
- 目的を明確にすることで素早く読める
- 繰り返しで記憶に定着させる
- アウトプットして活用しなければ意味がない
- 具体的な方法
- 1回目で重要箇所のあたり付け、2回目で「つまり読み」、3回目でアウトプットを意識した読み込み
- ノートやブログに学びのエッセンスと行動プランを書く
- 具体的な行動に移す
このブログでこのように本の内容を書くのも、アウトプットの一環です。読んだ本の要約や学びのまとめを継続し、日々の生活に役立てたいと思います!
それではまた。
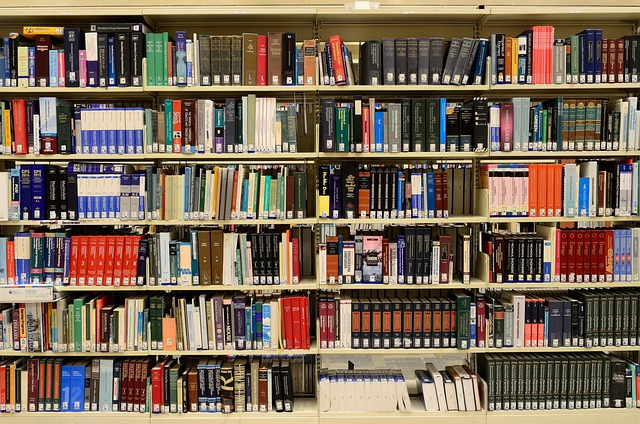


コメント