お読みいただきありがとうございます。
sstです。
今後、ブログで文章を書いていくうえで、学んだことをわかりやすくまとめて伝えるスキルは必要だと思い、勉強系の本を読んでいます。
まだ数冊程度ですが、個人的にいいなと思った本に出合えたので、紹介したいと思います。
タイトル:すべての知識を「20字」でまとめる
著者:浅田 すぐる
本の内容はタイトルの通りで、なぜそうするか(why)、なにに焦点を当てるか(what)、どうやってやるか(how)が説明されています。
※このwhy、what、howは本の中でも重要なキーワードです。
著者の浅田氏は、学んだことを忘れないために必要なことは以下の3点であると述べています。
- 目的の明確化
- 思考整理
- 端的な要約
以下、本について簡単に紹介します。
- なぜ20字要約が必要なのか
- 要約の基本
- 具体的な方法
- 学びを人に説明する
なぜ20字要約が必要なのか
皆さんは読んだ本の内容を覚えているでしょうか。
私の場合、なんとなく覚えているけど、簡単に説明して、と言われてもできない、ということがほとんどです。
それはなぜかというと、端的に説明できる形として自分の中で整理できていないから、なんですね。
この、「端的に」「整理」というのがポイントだと思っています。
当たり前のことですが、数行にもわたるような長い文章で説明された内容は、記憶しづらいです。
それに対し、1行程度のエッセンスならどうでしょうか。それも20字程度の。
圧倒的に後者の方が覚えやすいと思います。
じゃあ、数百ページもあるような本の内容を20字程度にまとめるなんてできるのか?という疑問が出てくると思いますが、それを実現するために必要なポイントが制約です。
要約の基本
具体的にどんな制約をかけるのか?
著者の浅田氏は、トヨタ自動車での勤務時代に、3つの制約条件下での資料作りを叩き込まれたそうです。
その制約条件が以下の3つです。
- 紙1枚に収める(基本はA4、場合によってはA3)
- 枠内に収める
- テーマから逸脱しない
働いていればわかると思いますが、説明資料を紙1枚にまとめるのは結構大変です。
過不足なくはもちろんのこと、要点を絞ることが要求されます。心配だからと余計な情報を盛り込んでいると、簡単に2ページ以上になってしまいます。
こうした制約条件の下で、何百枚もの資料を作る経験を通じて身についたのが本質をつかむ力とのことです。
本質とは何か?著者は、
多くの事象にあてはまる「よりどころ」
としています。エッセンスとも言えるかもしれません。
この本質を、本の著者の言葉そのままではなく、かみ砕いて自分なりの言葉で人に説明できるようにする過程で思考が整理され、端的に覚えやすい表現で頭に記憶されるのだと思います。
慣れないうちは、紙にキーワードを書き出すなどして情報を整理しながら、頑張って本質を見つけ出すことになるのだと思いますが、とにもかくにも数をこなして経験を積むことが重要と言っています。
具体的な方法
20字の要約のために、著者が提示しているのは以下で、これを20字インプットと呼称しています。
- 紙とペンを用意 (PCはNG)
- 目的を言語化する
- 本を読んで、目的に合った言葉を16個以内で抽出
- 言葉をグルーピングして、複数の言葉に関わるキーワードを考える
- 20字程度にまとめる
最後にまとめた20字が、自分の目的にあった本質になります。
ここまで言われると気が付くかもしれませんが、本の趣旨と自分の目的は必ずしも同じテーマである必要はないのです。目的をもって本を読み、そこから学びを得ることが重要ということだと思います。
もちろん、本の趣旨に沿った本質を抜き出してまとめるということも意味のあることだと思います。
ポイントは、本を読む目的を言語化することです。読みながら、たまに目的を思い出すために、目的のメモを見ることを推奨しているくらいです。私には心当たりがありますが、本を読んでいるとついつい読むことに集中してしまって、もともとの目的を忘れてしまうんですね。それだけは防ぐ必要があるわけです。
ここまでで、本の内容を20字の本質にまとめる方法がわかりました。
これは、いわば自分のための手法です。この20字だけを誰かに伝えても、なんのこっちゃ、ということになるので、人に説明する(=理解してもらう)ためには、別の型があるのです。
それが、why、what、howです。
学びを人に説明する
ここまでで、学んだ内容を要約する方法について簡単に紹介しました。ここからは、それを人に説明することについて考えてみます。
普段、人に何かを説明するとき、何を意識しているでしょうか。
私は、話を聞いてくれる人が、背景知識としてどこまで知っているかをイメージしたうえで、話の内容が複雑なものか、単純なものかで、結論と理由などをどんな順序で話すかを決めています。
複雑な内容だったら、聞いている人が不安にならないように先に着地点(=結論)を示したうえで、詳細を説明します。単純なものだったら、聞いている人も聞きながら着地点がわかると思うので、詳細→結論の順序です。
ただ、この本を読んでから、人の理解の仕方には大きく3通りあることを知りました。
それが、2W・1Hのwhy(なぜ)、what(なに)、how(どうやって)です。
職場の上司や同僚、友人を思い返したときに、そのような心当たりはないでしょうか。
理由や背景に焦点を当てて納得してもらおうと思っていたのに、実現方法をやたら突っ込まれるとか、具体的な内容を聞かれるとか。
それは、話を聞いている人の理解の仕方が、whyではなく、howやwhatを重視するタイプだから、のようです。
著者は、トヨタ自動車勤務時代に上司から数多くの突っ込みを受けるなかで、このwhy、what、howの3つの視点での説明が重要であることに気が付き、これらを盛り込むことで突っ込みを受けることが減っていったそうです。
この3つを網羅することで、聞いている人は、きちんと説明してくれた、と感じやすくなるそうなんですね。
もちろん、根本的な論理がしっかりしていないと文字通り話にならないので、筋の通った内容であることは必要条件です。
更に、著者はこれらの3つを、各3つ程度以内で項目を挙げて説明するとよいとも言っています。多すぎると、聞いている方もポイントがわからなくなってしまうので、ここでも制約をかけるわけです。
以上をまとめると、私にとってのこの本での学びは、
目的・制約で要約し、2W1H型で説明する
ですね。日々の仕事にも生かしていきたいと思います。
それではまた。
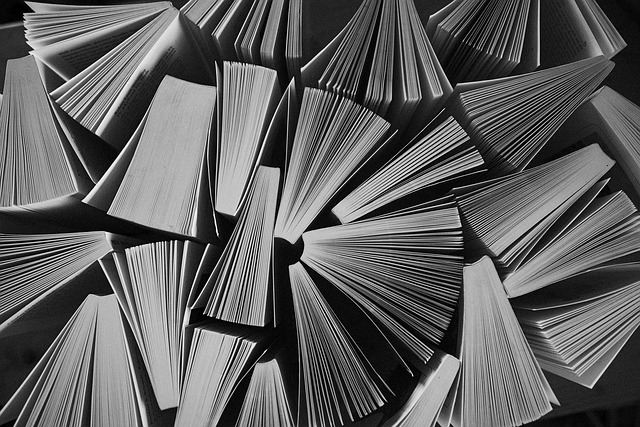


コメント